オーガナイザー
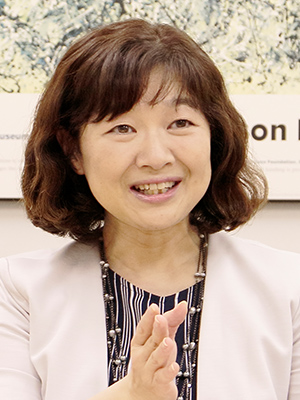
日本ケロッグ合同会社
執行役員 経営管理・財務本部長(CFO)
池側 千絵氏
新卒でP&Gジャパンに入社して以来、外資系企業数社のファイナンス部門に勤務。P&Gでは、家庭用洗剤・紙製品・ビューティケア事業部門などで担当事業の財務業績向上に取り組み、また日本支社全体の利益・資金管理と報告、経理、税務、アジアHQでの研究開発・販売管理費管理業務など幅広いファイナンスの専門業務も歴任。その後、日本マクドナルドのフランチャイズ事業担当財務部長、レノボ・ジャパンのCFOを経て現職。同志社大学卒、慶應大学院経営管理研究科在学中。
参加者

株式会社フィリップス・ジャパン
CFO
秋田 千収氏
新卒にてP&Gジャパンに入社し、約13年間ファイナンス部門に勤務。紙製品の事業利益管理、アジアの生産統括の効率化、取引制度改革、グローバルプレステージスキンケアの収益計画などを担当。2009年フィリップスに転職。ヘルスケア事業のコントローラー、戦略・事業企画、ヘルスケアの関東圏の営業・サービス統括を経て、2015年より現職。東京大学法学部卒。

株式会社すかいらーく
取締役執行役員 CFO
北村 淳氏
P&G(日本・米国)に14年間勤務し、事業部ファイナンスアソシエイトディレクターを歴任。その後、ティエヌティエクスプレスで専務取締役経営管理本部長を務める。2013年、すかいらーくに入社し、財務本部全社経営分析グループディレクターに着任。2016年から執行役員CFO、2017年より現職。東京大学経済学部卒。
多角的に分析してプランを提案する
ファイナンス
まずは皆さんのプロフィールを簡単に教えてください。
池側氏:私は新卒でP&Gのファイナンス部門に入社した後、利益管理や投資分析・新商品開発のサポートなど、主にビジネスサイドのファイナンスの仕事に携わりました。後にはアジアHQでの予算管理や日本・韓国の税務も経験しています。その後、日本マクドナルドのフランチャイズ事業担当財務部長、レノボ・ジャパンのCFOを経て、現在は日本ケロッグの経営管理・財務本部長を務めています。
秋田氏:私もP&Gのファイナンス部門に入って、13年ほど在籍しました。若いうちから経営の意思決定に関わることができ、やりがいとともに早く成長できるのではないかと考えたのが入社の理由です。P&Gでは、カテゴリーの事業計画を立てたり、アジア全体のコストやサプライチェーンの最適化を考えたり、グローバル10数カ国の収益率をどうしたら高められるかを考えたりしました。2009年にフィリップスに移り、ヘルスケア部門のコントローラーを務めた後、いったんファイナンスを離れて4年ほど関東圏の営業・サービス部門の責任者を務め、2015年から日本のCFOに就いています。
北村氏:私もP&Gのファイナンス部門に入社しました。P&Gに決めたのは、こういうビジネスパーソンになりたいと思える先輩社員が多かったからです。私はビジネスファイナンスが中心で、コスト分析・利益予測・プロジェクト分析などをよく行いました。アメリカのP&Gでファイナンスを担当していたこともあります。ジレットのM&Aの際には、ジレットの日本法人を統合するために、ジレットジャパンのファイナンス部門のトップになりました。2009年、ビジネスファイナンスだけでなく経理、財務、税務などを含んだフルパッケージのファイナンスを経験したいと考え、TNTエクスプレスに入社。次に、ヘッドクオーターの仕事をしてみたいと思い、2013年にすかいらーくに入社し、FP&Aのヘッドを経て、2016年からCFOを務めています。
自分がリードして利益を高められたエピソードを教えてください。
 秋田氏:P&Gでパンパースの生産統括ファイナンスを担当した際、生産設備の入れ替えのタイミングで、アジア&パシフィックの生産拠点をどう統合するかを考えたのは良い経験になりました。いくつかの選択肢の中から人員・サプライチェーン・物流などを考慮した財務計画や、短期・長期のメリット・デメリットを多角的に分析した上で、最終的な提案にとりまとめたのです。やりがいの大きな仕事で、視野が広がりました。
秋田氏:P&Gでパンパースの生産統括ファイナンスを担当した際、生産設備の入れ替えのタイミングで、アジア&パシフィックの生産拠点をどう統合するかを考えたのは良い経験になりました。いくつかの選択肢の中から人員・サプライチェーン・物流などを考慮した財務計画や、短期・長期のメリット・デメリットを多角的に分析した上で、最終的な提案にとりまとめたのです。やりがいの大きな仕事で、視野が広がりました。
北村氏:P&Gはそういった仕事が多かったですね。私もP&G時代には、いくつかのプランを立て、数字に落として比較するプロジェクトを何度も経験しました。一方で、予算達成をミッションとしたファイナンスの仕事にも携わりました。たとえば、ジレット統合の際は「シナジーを出して欲しい」と要求されましたが、ポストM&Aでは通常業務に加えて統合の準備やメンバーの不安払拭のための取組などやるべきことが多いなかで売上やコストシナジーを実現するのは簡単ではありません。私は部門の責任者たちと徹底的に話し合い、どうしたら日本市場で勝負できるのかを考え、最終的には新商品で一点突破するという結論に達し、成功を収めることができました。意思決定の重要性を深く理解した一件です。
ファイナンスの冷静な決断がビジネスを救う
Finance部門はどのようにビジネスの成長に貢献するのでしょうか?
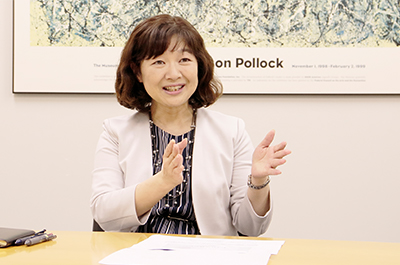 池側氏:P&Gの場合、ビジネスファイナンスが初期段階から新商品のプロジェクトチームに入っています。原価や利益を冷静に計算し、十分な利益を出すための売上目標と利益目標を明確に設定して、マーケティングや営業のメンバーの仕事の方向性を決め、チームをリードしていくのがその役目です。目標を設定すれば、皆がそこに向かって無駄なく動けるようになる。ファイナンスがつくる目標値が、チームに欠かせない目印になるのです。もちろん、途中で予定より原価が高くなるなどの「事件」が起きることもよくありますし、ファンナンス視点では厳しい(利益目標を達成するのが難しい)と感じる新商品もあるのですが、そうしたときもメンバーには明るく接して、チームの雰囲気を壊さないことが大切です。原価の上昇などを早めに見越して、目標値を調整したり原価削減案を募ったりしながら、きちんと利益が出る商品を世に出せるように伴走するのもファイナンスの仕事です。
池側氏:P&Gの場合、ビジネスファイナンスが初期段階から新商品のプロジェクトチームに入っています。原価や利益を冷静に計算し、十分な利益を出すための売上目標と利益目標を明確に設定して、マーケティングや営業のメンバーの仕事の方向性を決め、チームをリードしていくのがその役目です。目標を設定すれば、皆がそこに向かって無駄なく動けるようになる。ファイナンスがつくる目標値が、チームに欠かせない目印になるのです。もちろん、途中で予定より原価が高くなるなどの「事件」が起きることもよくありますし、ファンナンス視点では厳しい(利益目標を達成するのが難しい)と感じる新商品もあるのですが、そうしたときもメンバーには明るく接して、チームの雰囲気を壊さないことが大切です。原価の上昇などを早めに見越して、目標値を調整したり原価削減案を募ったりしながら、きちんと利益が出る商品を世に出せるように伴走するのもファイナンスの仕事です。
北村氏:P&Gは、クロスファンクションチームからのインプットや市場調査のデータなどからファイナンスが事業P/L、プロジェクトP/Lやキャッフュフロー分析等を行います。この手法が確立しており、蓋然性がありました。対して、これはおそらくどの企業でもそうですが、特定部門だけで組み立てたP/Lやキャッシュフローは当たらないことが多い。”こうあって欲しい“という希望的な観測から見込が甘くなってしまったり、管理会計などの知識が不足しているからです。しっかりと収益性を見極めて信頼できる目標値を立てるのはファイナンスの役割ですね。
池側氏:一方で、ファイナンスは、新商品が十分に売れず、販売が終わってしまった際の「後始末」にも積極的に関わります。チームメンバーと一緒になって、残った原材料を再利用したり、製品在庫の価格を下げて販売したり、在庫や機械を処分する際に、きちんと税務処理をして節税します。そこで少しでも損を減らすことが、事業部全体の利益に大きく関わってくるからです。リスクをとって新規ビジネスの決断をするのは重要ですが、失敗した場合の損を最小限に抑えて、次の投資に備える。そのようなバランスをとるのもファイナンスの重要な仕事なのです。
秋田氏:付け加えると、商品の販売を打ち切るときの「英断」を行うのも、ファイナンスの仕事、課せられた使命でもあります。関係するメンバーはどの商品にも必ず思い入れがありますし、売上・シェアを上げることが必要ですから、販売の打ち切りは決めづらいのですが、実際は販売を早く止めるほど傷が浅くなるケースが多く、また低収益の事業に向けられていたリソース・投資をより成長が見込める分野にシフトすることができます。そうしたとき、ファイナンスの冷静な提案がビジネス全体を救うのです。
P&G以外の職場ではどうでしょうか?
 池側氏:まず外資系企業と日系企業の一般的な違いを言えば、日系企業では経営企画や商品部やマーケティング部、研究開発部内の企画の方が細かい利益管理などをされているようです。一方、外資系企業では、ファイナンスのメンバーが各部門、各プロジェクトチームに入って利益管理をします。私の目から見ると、ファイナンスのメンバーが行う分、外資系企業のほうが、妥協なく厳しい目標設定や的確な利益管理ができているのではないかと感じます。実際、外資系企業のほうが全体的には利益がよくなっています。
池側氏:まず外資系企業と日系企業の一般的な違いを言えば、日系企業では経営企画や商品部やマーケティング部、研究開発部内の企画の方が細かい利益管理などをされているようです。一方、外資系企業では、ファイナンスのメンバーが各部門、各プロジェクトチームに入って利益管理をします。私の目から見ると、ファイナンスのメンバーが行う分、外資系企業のほうが、妥協なく厳しい目標設定や的確な利益管理ができているのではないかと感じます。実際、外資系企業のほうが全体的には利益がよくなっています。
北村氏:私はP&Gで、いわばファイナンスの「筋トレ」を積んできたと思っており、今はその力を外で活かしている感覚があります。ただ、外に出てわかったのは、私がP&Gで学んだファイナンスは「ディフェンシブ(防御的)」だったということです。もちろん、役割上、ファイナンスはある程度守りを固める必要がありますし、事前に多くのリスクを検討し保守的にすすめることが良い方向に働くケースも多いのですが、ビジネスで大きな成功を成し遂げる際には、守りを固めるだけではうまくいきません。今、私はそのことを実地でトライ&エラーしながら学んでいる最中です。
秋田氏:私の場合、P&Gの内と外というよりも、ジュニアからシニアに成長する過程で視点が変わりました。シニアになって気づいたのは、成果は戦略のみならず社員一人ひとりのコミットメントやモチベーションに大きく依存するということです。ですので、営業、サービス、バックオフィスにかかわらず社員一人ひとりの成果の積み上げをとても大切に考えており、社員の皆さんへの感謝の気持ちを常に忘れないようにと心がけています。もちろん、だからといって数字には妥協できないのですが。
北村氏:私の実感としても、人に対する投資が最もリターン率が高いと思います。ただ、もしかしたら秋田さんや私がそう考えるのは、P&Gが「ピープルマネジメント」を重視していることも大きいかもしれませんね。マネジャーになれば、そのミッションの50%は人材育成だと教えられる会社ですから。
池側氏:私が感じるのは、業界によってファイナンスのスタンスが違うことです。たとえば、P&Gは各ブランドへの宣伝広告費の投資対効果を細かく見て管理する会社ですが、私が勤務した飲食業界では基本的に商品ごとの宣伝広告費の投資効果をそこまで細かく見ていませんでした。なぜかといえば、飲食店は宣伝を見て来られたお客様が他の商品を選ぶ場合も多く、それでも店舗全体の売上増があればそれでも構わないからです。そうした点はケースバイケースで、ファイナンスが自分で考えながら適応していかなくてはなりませんね。
まとめ
前編では、CFOである3名の皆様のこれまでご経歴、Finace部門がどのようにビジネスに関わるのかをお話いただきました。後編では、CFOに求められること、醍醐味、CFOを目指す人へのアドバイスをいただきました。引き続き、後編もお読みくださいませ。




 記事一覧に戻る
記事一覧に戻る  業界カテゴリー
業界カテゴリー


 LinkedInを見る
LinkedInを見る