キャリア観を考える上で、転機となったのが
グローバルな環境で活躍する「外資系トップ」として、キャリア観などを教えてください
 日本にいると基本は終身雇用といいますか、「他の世界なんて」「ここが一番だ」という感じが強い。ところがアメリカに行くと、みんな自分のキャリアのことを、いつも考えています。そして、いろんなオポチュニティをいつも模索している。アメリカ人にすれば、同じ会社にずっと働いていると、新しいオポチュニティに出会えなくなる、ということになるんです。チャレンジングな人ほど、いろんなオポチュニティに出会えて、会社をどんどん替わっていくというわけです。
日本にいると基本は終身雇用といいますか、「他の世界なんて」「ここが一番だ」という感じが強い。ところがアメリカに行くと、みんな自分のキャリアのことを、いつも考えています。そして、いろんなオポチュニティをいつも模索している。アメリカ人にすれば、同じ会社にずっと働いていると、新しいオポチュニティに出会えなくなる、ということになるんです。チャレンジングな人ほど、いろんなオポチュニティに出会えて、会社をどんどん替わっていくというわけです。
転機になったのは、あるトレーニングで企業再生の専門家に出会ったこと。彼は、ターンアラウンドのプロで、三年間で結果を出すと、また次の三年間に向かう、という経験を何クールもやってきた人でした。こんな仕事があるんだ、こういう生き方もあるんだ、と思いました。まさに経営のプロ。これはかっこいいな、と思って。私はマーケティングのプロになりたいと思って、プロになった。ゼラルマネージャーになったら、次は絶対に経営のプロの道だ、と思ったんです。請われて経営をお願いされるようになれたら、どれほど素晴らしいだろう、と。だから、このときゴールを決めたんです。経営をやってみたい。小さな会社でもいいから、外資系の社長になるんだ、と。
日本クラフトフーズの経営者として
経営の仕事は、日本クラフトフーズが、初めてです。新しい業務分野や見識を高めるといったことは必要ですが、戸惑いはあまりなかったです。P&Gでのブランドマネージャーの時代から、小さな会社を経営している気持ちでやっていましたから。ゼネラルマネージャー時代は、P/Lも見ていましたし。それより何より、社長になって改めて思ったことは、社員の士気をいかに高めていくか、ということの大切さでした。ビジョンを作り、人々を鼓舞し、モチベートして、結果を出す。これこそまさに経営者の仕事です。たとえば年一回、直接の部下ではない全マネージャーと一時間、一対一のミーティングを続けてきましたが、これをマネージャー以外にも拡げようと思っています。これは私自身の学びの場でもあるんです。会社や仕事に関して、同じ目線で語れるのは楽しいですしね。 そして実はモチベーションを高めたり、リコグニションを与えるのに、日本語は難しいと改めて気づきました。これは、英語のほうがしっくりきます。今度は日本語でも、英語のようにうまく誉めたりモチベーションを高めたりできるようになりたいと思っています。
外資系からキャリアを始めましたが、聞けず、書けず、しゃべれずのスタートでした
「英語力」というテーマですが、グローバルな環境で、英語を身につけてビジネスを動かしていくことの難しさはありましたか?
 外資系からキャリアを始めたんだから当然、英語はできたんでしょう。そんなふうに思われることもあるんですが、実はまったく違います。聞けないし、書けないし、しゃべれなかった。本当ですよ。
外資系からキャリアを始めたんだから当然、英語はできたんでしょう。そんなふうに思われることもあるんですが、実はまったく違います。聞けないし、書けないし、しゃべれなかった。本当ですよ。
でも、使わないといけない状況に追い込まれたら、できるようになるんですね。自分でいわゆる「英語の勉強をした」という記憶はほとんどないです。基本、オンザジョブ。それこそレポートも英語で書かないといけないし、外国人の上司へのプレゼンテーションもしないといけないし、会議だって英語でやらないといけない。やらざるを得ないと、できてくるものなんですね。だから私が思うのは、やっぱり仕事で使わないと英語は上手にならない、ということです。
実は日本クラフトフーズでも、かながわサイエンスパークにあるR&D部門が社員の発案で金曜日を「英語デー」にしています。社内ではすべて英語でコミュニケーションする。日本人だけの小さな会議でも、です。これはとても効果的だと思っています。例えば営業職などは、日本市場を対象にしていれば、日本語だけで仕事ができないわけではない。でも、英語ができれば、手に入る情報量が圧倒的に変わるんですね。世界各国が発信する情報が手に入るし、世界中の成功事例をインプットできる。世界の店頭で何が起こっているか、業態はどう変わりつつあるか、消費者ニーズはどんな変化を見せているか。それを知ることが、日本での仕事にプラスにならないわけがない。世界の市場の変化に対して、私たちがやらないといけないことは何か。どんどん、先に先に、ラーニングしていくことができる。これは大きな強みになります。もちろん、日本の成功事例を海外にシェアすることもできます。英語ができるだけで視野が広がるし、モノの見方が多面的になる。しかも、それだけではないと思っています。英語ができれば、仕事がもっともっと、楽しくなるんです。
グローバルコミュニケーションには、相手をモチベートできるスキルが必須
その仕事にどんな意味があるのか。会社に対してはどんな意味があり、あなたの部署にはどんな意味があって、あなた自身にはどんなベネフィットがあるのか。
これをちゃんと説明できないといけない。しなかったときのデメリットも言えないといけない。これがグローパルでは、当たり前に求められるんです。そうでないと、「どうして私があなたの仕事をしないといけないのか」ということになる。グローバルコミュニケーションとは英語をしゃべることだ、と思う方もいるでしょう。でも、相手をモチベートできないと、コミュニケーションにならないし、仕事は前にも進んでいきません。共通の目的を見出し、それに同意してもらって、自ら責任感を持ってもらって、モチベーションを上げて、「やるぞ」と思わせる。そういうコミュニケーションが求められるんです。アメリカにいた三年間で一番変わったのは、この姿勢でした。それまで本当にシンプルな文化の中に暮らしていたんだとはっきり気づかされました。日本人同士のコミュニケーションはラクなんです。アラインメントにも、エンゲージメントにも時聞を費やさなくてよかった。でも、日本に戻ってからは、日本人の部下にもそれをやりました。やらないと自分が気持ち悪くて(笑)。やってみると、私も部下も、とても心地よく仕事ができたんです。
Text by 上阪 徹
(書籍「外資系トップの英語力」では、井上氏インタビューについて、さらに詳しい内容を掲載しています)

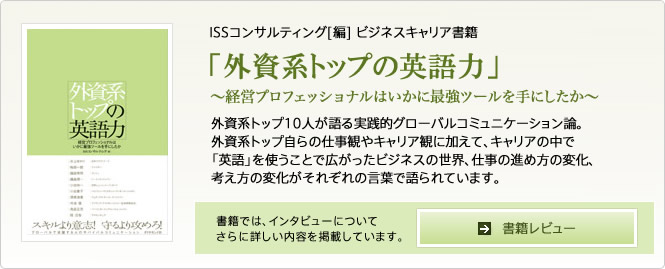
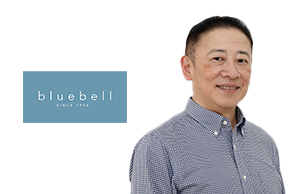



 記事一覧に戻る
記事一覧に戻る  業界カテゴリー
業界カテゴリー


 LinkedInを見る
LinkedInを見る