仕事に強い使命感と責任感を持ち、命懸けになれる人がプロだと思う。
大学を出て通商産業省(現・経済産業省)に入られた理由は何だったのでしょうか?

自分としては「就社」ではなく「就職」だという意識が強くあり、入る会社より、やる仕事を優先して考えました。大学のときから社会への貢献度の高い仕事をしたいと考えていて、当時大きなテーマだった日米の貿易摩擦や発展途上国への経済支援等に実質的に関われる通産省に興味を持ちました。省庁訪問で通産省に行ったときに、お会いした方々の話が興味深く、人間的な観点から魅力を感じたことも通産省に決めた理由の1つです。
自分としては、官僚になるための職場ではなく、自分がやりたい職に就くことができるフィールドとして通産省を位置づけていました。ですから入省してからも、通産省の職員であることを意識するよりも、自分の仕事に意義と価値を見出し、それに全力を注ぐことをポリシーにしてやってきました。
2003年にマイクロソフトに移られました。経緯とお仕事の内容をお聞かせ下さい。
通産省では担当業界は数年単位で変わるので、“ジェネラリスト”になっていきます。私は“プロフェッショナル”になるために、もっとスペシャリティ(専門性)を磨く必要性を感じていました。市場に近いところで社会に貢献する仕事、と言う点と、自分が15年間通産省で培った経験を少しでも活かせる企業・業界を中心に転職を検討しました。マイクロソフトが私に提案してきた職務が、これまでの経験も活かせて、更にいろいろな方向にキャリアを伸ばしていけそうだと思い決断しました。
マイクロソフトでの最初のタスクはコーポレート・アフェアーズと言って、分かりやすく説明しますと、会社の社会的イメージを向上させることが目標に設定されました。入社した当時はオープンソースが流行りだした頃で、アンチ・マイクロソフトの風潮が高まりつつありました。こうした風潮への対策を練ったり、マイクロソフトが積極的な利益の社会還元をしていることを世の中へ広く伝えるプロジェクトを立ち上げたりしました。具体例を挙げますと、障害者のITトレーニングの支援、教育機関へのPC提供、教師向けのPC操作指導テキストの制作・配布といったようなことです。
約1年後に現職の公共インダストリーに移動しました。公共インダストリーは、官公庁、自治体、教育機関、医療機関などに対して営業活動を行う部署です。経済原理だけでは動かない非営利である相手に対し、社会貢献的な部分を合わせた提案を行い、当社製品を活用いただけるようなプロモーションを行っています。
マイクロソフトの今後の方向性、展開について教えてください。
先進国市場が成熟しつつあるなかで、日本市場だけは公共部門も含めて伸びており、アメリカ本社も日本への投資にとても積極的です。当然、我々はその投資に見合うだけのリターンを生まなければいけない。マイクロソフトの製品は相応の競争力を持っているので、これまでは「プロダクトアウト」的な発想でもやってこられました。しかしこれからは、お客様の側に立った、「デマンドプル」の発想が必要になる。お客様が抱えている課題を把握して、お客様の立場に立ったカスタマイズド・ソリューションを提供しなくては評価されません。そのために、パートナー様との連携を最大限に活用し、共同でマーケティングを行って需要を掘り起こしていくことに注力したいと考えています。
前職と比べて、仕事の進め方などで違いを感じることはありましたか?
前職との最大の違いは、マイクロソフトは実績の検証と明確な数値化を徹底していることかと思います。弊社ではパフォーマンスが常に問われるし、それが実際に数字で現れる測定可能な評価基準になっている。顧客満足度、従業員満足度といった、数値にして測定しづらいことも、何とか数値化して検証しようとしますね。それは業績評価をきちんとするためでもあり、ベストなサービスをお客様に提供するためでもある。また、評価に情実が入り込まないように、すなわちアンフェアにならないようにしているし、仕事で出した結果、実績で昇進などが決まりますから、部下と上司の関係もいい意味で対等です。上下関係が逆転することの少ない役所と比べると、緊張感があり、良い刺激になります。そういった点は、外資系の良いところだとも思います。
マネージメントとして人を動かす上で大事なことは何でしょうか。
 仕事を進める上で1つ気を付けているのは、“何をしようとしているのか”という目的・目標を、スタッフ全員常にシンプルかつクリアにしておくことです。そしてゴールを達成するために、みんながどう動くのがベストかを考えます。ともすると、あれもしなきゃ、これもやらなければ、と手を広げ、結局は全部中途半端になって成果に結びつかない。それを避けるために、目標達成の期限を決め、検証可能なストーリーを作って見直しながら取り組むことをスタッフには奨励しています。検証可能であればPDCA(Plan-Do-Check-Action)のマネジメントサイクルに基づいて、常に軌道修正できますから。営業数字を達成するために、ゴールから逆算してシンプルで検証可能なストーリーを考えるのは、とてもクリエイティブなことだと思っていますし、これを個人レベルでも、きちんと管理・実行できる人は優秀な人材だと思います。また、常に前向きな姿勢を持つことも良い仕事をするのに必要な要素です。
仕事を進める上で1つ気を付けているのは、“何をしようとしているのか”という目的・目標を、スタッフ全員常にシンプルかつクリアにしておくことです。そしてゴールを達成するために、みんながどう動くのがベストかを考えます。ともすると、あれもしなきゃ、これもやらなければ、と手を広げ、結局は全部中途半端になって成果に結びつかない。それを避けるために、目標達成の期限を決め、検証可能なストーリーを作って見直しながら取り組むことをスタッフには奨励しています。検証可能であればPDCA(Plan-Do-Check-Action)のマネジメントサイクルに基づいて、常に軌道修正できますから。営業数字を達成するために、ゴールから逆算してシンプルで検証可能なストーリーを考えるのは、とてもクリエイティブなことだと思っていますし、これを個人レベルでも、きちんと管理・実行できる人は優秀な人材だと思います。また、常に前向きな姿勢を持つことも良い仕事をするのに必要な要素です。
“背水の陣” “リスクをとる”そして、結果に責任を負うことが大事。
大井川さんが考えるプロフェッショナルとは、どのような人材ですか?
仕事に対する情熱と責任感を強く持っている人。そして大きなリスクのある仕事であっても、“目標を達成できなかったら自分が責任を取る”くらいの気概で結果に対して自身をコミットできる人、ですね。“背水の陣”の覚悟と言うか、最後まで“自分の責任”として前のめりで仕事に取り組む姿勢が大事です。
プロフェッショナルということと、いわゆる専門家、エキスパートであることは別のことであると思います。専門分野の知識や経験がいくら豊富であっても、目の前の課題から逃げるようなことでは、決して成果を上げることはできないと思います。結果に対する責任を取れる人だけが本当に良い仕事ができると信じています。
ではITプロフェッショナルとは、どのような人材だとお考えですか?
ひとつ良い例があります。以前、パートナー様と一緒に構築したお客様のシステムでトラブルが発生し、その修復に当社テクニカルサポートチームと一緒に取り組んだことがありました。なかなか問題が解決せず、昼夜問わずの作業がつづき、全員が疲労困憊する中、作業を行うサポートチームのスタッフ誰一人文句一つ言わずに黙々と作業をするのですよ。作業の過酷さへの不満もそうですが、自分が作ったシステムではない状況下で、他者への不満も言わず、自分の仕事として全力を尽くす。そのときの彼らの、仕事に対する責任感、モチベーションの高さと、お客様へ提供するサービス品質へのこだわりに、いたく感動したのを覚えています。これこそがプロだなって。
ITのプロとは、ITを通じてお客様や社会が持っている課題を解決することに、本当の意味でコミットできる人であると考えます。様々な課題の解決のためには、もちろん自らも技術的に高いスキルを身につけていることが求められるでしょう。ただ、それだけではなく、自分の仕事に対して誇りと使命感を持ち、なおかつそれを高める努力を継続する人、そして、お客様や社会が抱える課題の解決に不退転の決意で臨める人、そんな人が、どんな場面でも仕事に集中して最大のパフォーマンスを出せるのだと思います。
IT業界の経営者に求められるものは何だと思われますか?
 IT業界に限ったことではありませんが、つねにお客様の立場で考えるプロ意識と、人をマネジメントする能力でしょうね。社員のモチベーションを高いレベルで維持し、シンプルな目標を示して、その達成に向けて社員がみずから努力するように巻き込んでいく能力。結局は人格の勝負になると思います。いかに専門的な知識、スキルを持っていても、人格が伴わなければ人はついてきてくれませんから。
IT業界に限ったことではありませんが、つねにお客様の立場で考えるプロ意識と、人をマネジメントする能力でしょうね。社員のモチベーションを高いレベルで維持し、シンプルな目標を示して、その達成に向けて社員がみずから努力するように巻き込んでいく能力。結局は人格の勝負になると思います。いかに専門的な知識、スキルを持っていても、人格が伴わなければ人はついてきてくれませんから。
IT業界で言えば、先ほどの人的資質を備えていて、かつ、IT知識を有し、お客様が困っていること、抱えている課題を聞き出し、理解する能力が必要かと思います。その課題をITで解決するためのシナリオを、既存製品ありきではなく、顧客ニーズ主導で描いて提案できることが、IT企業の経営者には必要だと思います。
有難うございました。


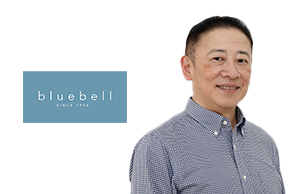



 記事一覧に戻る
記事一覧に戻る  業界カテゴリー
業界カテゴリー


 LinkedInを見る
LinkedInを見る