DXは目的ではなく、経営を変革するための“手段”にすぎない──。
小林製薬 CDO(Chief Digital Officer)石戸亮氏はそう語ります。
広告代理店からキャリアを始め、外資ITやスタートアップ、伝統ある日系企業を経てたどり着いたのは、「肩書きを消すために存在するCDO」という逆説的な哲学でした。本インタビューでは、その原点から現在、そして未来への展望までを紐解いてまいります。
「理系と文系の“間”に立つ存在として、ビジネスの世界へ」

千葉県ご出身とのことですが、上智大学の理工学部を選ばれた理由は?
もともと国語や社会が苦手で、数学と物理が得意だったことが大きな理由です。父がIT業界で働いていたことも影響しています。「これからはITの時代だ」という父からのアドバイスをかなり大雑把に捉えていました。大学時代には父親の紹介で秋葉原のIT機器のジャンク屋でアルバイトをしたこともありました(笑)。
上智大学に入学後、大学時代から起業されていたとか。
はい。理工学部でプログラミングなどに取り組む中で「この分野でプロとして突き抜けるのは難しいな」と感じたのです。一方で、ビジネス側と技術側の橋渡しができる人材がいないことにも気づきました。そこで、ちょうど学生起業が盛り上がっていた時期だったこともあり、地元・千葉県柏市でフリーペーパーのビジネスを立ち上げました。
なぜ柏だったのでしょう?
まず、柏は古着屋や美容室が密集していて、地域としての魅力がありました。それなのに多くの若者は原宿に流れていた。それがもったいないと感じて。地元の幼なじみで現在はスタートアップ企業のアソビュー株式会社の社長をしている友人と一緒に始めました。
かなり本格的に取り組まれていたのですね。
そうですね。3年生以降はほとんど大学に行かず、朝から昼は古着屋や美容室などに営業、夜はアルバイト、深夜に出版のための編集作業やクリエイティブ作業という生活でした。朝5時まで記事編集をして、3時間寝て営業に出るような日々が楽しかったのです。何が楽しいかと聞かれると難しいですが、それまで幼稚園から365日サッカー漬けで過ごしてきて、辞めた途端にぽっかり空いていた“熱中できるもの”が、自分にとってはビジネスだったのだと思います。ものすごく忙しかった一方で、自分の中で「間」に立つ役割を見出した原点だったと思います。
その熱中が、事業の成長にもつながった?
ええ。最初は企画書3枚で営業を行い、「お前らに発注できるか」と怒られながらも少しずつ発行部数を増やして地元メディアに取り上げられたり、地域のイベントと組んだり。売上も学生ながら年間で数百万円規模になっていきました。積み上げていく過程がとにかく楽しかったです。
サイバーエージェントへ入社後は、順風満帆でしたか?
全く逆で、入社から数ヶ月間は営業職として売上ゼロでした。同期はすでに大型案件を動かしていて、自分だけ取り残されている感覚が強く、完全に思考停止状態。焦りと自己否定の連続でした。毎週のように営業職経験の長い父に相談しては、「まずはやりきれ。やりきっても辛ければ辞めたらいい」と背中を押されていました。
そんな中、どう乗り越えたのですか?
とにかく「今じゃなくてもいい」と思うことにしました。父が営業のメソッドを教えてくれ、「BANT(※)を明確にして、2〜3年後を見据えて動くものだ」とアドバイスをくれたので、短期成果に縛られるのをやめたのです。そうしたら、地道なヒアリングが数ヶ月後に成果に変わっていくようになり、徐々に自信を取り戻しました。
※BANT: Budget(予算)、Authority(決裁権)、Needs(必要性)、Timeframe(導入時期)
マインドセットが変わったのですね。
はい。当時のサイバーエージェントには、月末に全社で達成メールが飛び交うような営業文化がありました。どうしても月末にはお客様に対して「今月何かありませんか?」という動きをしてしまっていました。ですが、お客様が本当に困るタイミングは月末ではないことも多い。年末の組織変更、来期の予算編成…そういう話を聞き取りメモしておいて、数ヶ月後に「その後どうですか?」と連絡すると発注につながったりする。それが営業の面白さだと気づきました。
その後、子会社で役員に就任された経緯は?
本社で結果を出し続けたことで念願の異動が叶い、子会社の営業マネジャーとして着任しました。ところがその後、営業役員が辞め、後任に指名されるかと思いきや「まだ人をまとめて導く力が足りない」という理由で任命されなかったのです。当時は15名ほどの部下の多くが年上で、経験豊富な方がいたにも関わらず、信頼して頼るということをせずに指示ばかり出していたのです。最終的には組織が崩壊し、全体会議で率直な意見をぶつけ合う場を設けられ、自身の至らなさを痛感しました。
そこからどう変わられたのですか?
「人を信じて頼ること」ができていなかったと深く反省しました。それからは一人で考えるのではなく部門内に2~3人の相談相手を持ち、都度対話を行いながら進めるスタイルに変えたのです。結果的にそれが組織の信頼を生み、ようやく人間性も認められ、役員に昇格することができました。
営業とデジタルの“間”に立つ存在として

「‘勢いのある営業’と‘堅実なコンサルティング’の橋渡し役として」
営業からコンサルティング部門に異動後、どのような挑戦があったのでしょうか?
営業では“できない経験”が多かった分、仕組み化やマニュアル化が自然とできました。だからこそ、若手営業向けに「こうすれば成果につながる」というフレームをつくることができたのです。ただ、異動先のコンサル部門は全く違う土俵でした。経験豊富なプロたちが揃っており、私の型は通用しませんでした。
まさに“勢いのある営業”と“堅実なコンサル”の文化の違いですね。
そうなんです。営業は勢いで案件を取りますが、強引に受注すると継続率が落ち、コンサル側がフォローに追われる。その結果、評価も下がってしまう。そこで、「良質な受注のためには営業教育が必要」と考え、営業経験のある私が勉強会や研修を企画しました。
石戸さんご自身が、“橋渡し役”になられたのですね。
振り返れば、常に「間に立つ」ことをやってきた気がします。営業とコンサル、文系と理系、現場と経営。それぞれを理解し、翻訳・統合する。CRM(顧客管理)もその一つで、営業視点とエンジニア視点をつなぐ仕組みとして自ら要件定義を行い、システムを構築しました。
すべてを自分で抱えるのではなく、繋げることを意識し始めたのもこの頃です。信頼できる現場メンバーがいれば、「自分からではなく、彼から伝えた方が良い」と自然に思えるようになりました。人を頼り、翻訳し、仕組みにしていく──。それが自分の役割なのだと、少しずつ実感し始めていました。
育児休暇と“働き方”の挑戦
「“父であること”を理由に退職を考えたあの日」
2社目の役員経験の後に、育児休暇を取得されたとのことですが、当時の社内状況はいかがでしたか?
1人目の子どもが生まれた時、週1日だけでも早く帰りたいと上司に相談しましたが、当時はまだそうした働き方が浸透しておらず、社内に異なる常識を理解してもらうような工夫や活動が必要でした。夜の会議や週末の行事も当たり前のように予定され、家庭との両立を考えると、自然と“育児休暇”を検討するようになりました。
かなりの反発もあったそうですね。
一部の経営層からは「営業責任者なのに数字はどうするのか」との厳しいご意見もありましたが、徹底して準備を整えることで徐々に理解が進みました。チャットツールやWeb会議の仕組みを整え、何かあれば即時対応できるようIT部門も巻き込んで説得しました。ですが、まだまだ<男性の育児休暇>が理解されにくい時代だったこともあり、一人で戦っている状況がメンタル的には厳しかったです。
当時、サイボウズ社の社長が育児休暇を取得したと話題になったこともあり、面識のない中、同社の青野社長に直接コンタクトを取り相談をさせていただきました。様々な助言をいただき、勇気をもらったことを覚えています。
私の育児休暇取得後は、社内の風土も変わっていった印象があります。何名かの男性社員からは「石戸さんが育児休暇を取得してくれたおかげで、取得しやすくなった」などと言っていただき、子どもをもつ社員も二人、三人、と徐々に育児休暇を取るようになりました。結果的に制度と意識の壁を壊せたことは、よかったと思っています。
その後のキャリアとして、Googleへ転職されましたが、その背景は?
当時、子会社の海外拠点を米国に作り、本気でグローバル展開にチャレンジする矢先、子どもの誕生で渡米は延期に。その後、ようやく渡米できる体制が整った時に、本社の事情で国内のとある事業責任者を任されることになりました。海外でチャレンジをしたく、数か月にわたり本社役員をはじめ様々な人と対話を続けましたが、最終的にグローバルへのチャレンジが難しいという結論に至り、転職する覚悟を決めました。東日本大震災もあり、「将来的に国内だけのキャリアではリスクがある」と感じたことも理由です。そんな時、Googleの村上憲郎会長と偶然食事をする機会があり、その出会いが背中を押してくれました。
極端を手放すことで見えた“自分らしいキャリア”

「2年間で3000時間──キャリアと家族のための挑戦」
Googleへの転職には、明確な目的があったそうですね。
はい。ビジネスで結果を出しながら、覚悟を持って英語を学習しようと思いました。きっかけは村上憲郎会長に「10年後、英語ができるかできないかで大きな差が出る」と言われたことでした。そこで外資系の一流企業で働き、結果を出しながらグローバルで通用する人材になるべく、英語に本気で取り組みました。
「2年間で3000時間、英語を学習する」と決め、平日は5時間、土日は10時間。髪を切る時間も惜しいので自分で坊主にし、Googleの社内イベントや飲み会もすべて断って、「やる」と決めたからには徹底的に自分を孤立させて学習に集中しました。 “英語に人生を懸けた時代”と言っても過言ではありません。
Googleでの経験は、働き方やキャリア観にも影響を与えましたか?
大きかったですね。ピアボーナスの文化、インクルーシブな風土、天才たちがつくるアルゴリズム──すべてが今の自分に活きています。ただ、振り返れば極端でした。2年間で3000時間英語を学習しましたが、家庭とのバランスをもっと取ることも大切だったと感じています。
極端な頑張り方を見直されたと。
はい。学生起業の頃から何かに取り憑かれたように走ってきましたが、常に全力疾走ではなく、長く成果を出し続けるために、少し余白を持って走ることも大事なのではないかと思うようになりました。子どもとの時間、家族との時間、それもキャリアの一部だと。
その後、イスラエル系のAI企業へ。どのような経緯でしたか?
最初は海外勤務ができる会社を探して転職活動をしていました。海外に拠点を持つ様々な日系企業と話しを進めていましたが、何か決め手に欠けていました。
そんな中、イスラエル企業の日本支社社長からお声がかかって。プロダクトの質が高く、親日のイスラエル文化がとてもフレンドリーで「これは面白い」と直感しました。IPOやM&Aの可能性もあるフェーズに対して、ダイナミックな変化への期待もありました。また、何よりもスタートアップ企業だからこそ、30代前半のうちにダイレクターになれるということも魅力でした。自身のキャリアとして年功序列型に適合していくよりも、「買収された時にタイトルもキャリアも一気に引き上げる」という逆算型の考え方のほうがしっくりきたことも決め手でした。
イスラエル発スタートアップと“営業メソドロジー”の衝撃
「Salesforce流“営業メソドロジー”との出会い」
イスラエル発のマーケティングテクノロジー企業に参画された背景を教えてください。
買収される前提ではなかったですが、プロダクト力と成長スピードを見て「これは近いうちにSalesforceやAdobeに買われるな」と感じていました。実際、その直感は的中し、約3年後にSalesforceによって買収されました。私にとってはIPO経験、グローバルPMI、そして“外資の営業”を体感できる絶好の機会でした。
イスラエル企業での経験はどうでしたか?
最高でした。開発はイスラエル、本社はニューヨーク。私自身は日本を担当していたのでイスラエル現地には行けなかったのですが、CEOやCTOがとにかく“親日家”で、日本の顧客要望を積極的に取り入れてくれたのです。日本では誰もが耳にしたことのある日系上場大手企業のニーズを直接ヒアリングし、開発に反映する──まさに“共創”の感覚がありました。
買収後はSalesforceでPMIを担当されたと。
はい。意図的なのかは分かりませんが、社内では買収の1年前から「Salesforce化」への準備が進んでいました。ツールやオペレーションをSalesforce基準に揃えておけば、PMI(Post Merger Integration)がスムーズになる。まさに計算されたM&A戦略でした。
Salesforceには2年ほど在籍しましたが、最も驚いたのは“営業メソドロジー”の完成度です。日本ではまだ珍しいレベルで、ブートキャンプから始まり、数値管理、KPI設計、CRM連動、すべてが科学されている。営業が“個人の勘”ではなく“システム”として機能していることに刺激を受けました。
Googleとはまた違う文化ですね。
Googleは「世界中の情報を整理し、誰もがアクセスできるようにする」という使命を掲げ、検索サービスを起点に発展してきました。その文化はオープンな議論や多様なアイデアを尊重し、社員一人ひとりの好奇心や探究心から新たなプロダクトを生み出す風土を育んでいます。
一方でSalesforceはCRMを起源とし、明確なバリュー(Customer Success, Innovation, Equality, Sustainability)を基盤に、顧客起点の体系化された営業・組織メソドロジーを強みとしています。そこから生まれるのは、再現性高く成果を出す仕組みです。Googleでの自由闊達な創造環境と、Salesforceでのシステマティックな実行力。両者の学びが、私のキャリアを支える二つの土台となっています。
Salesforceを離れる決断に至った背景には、どんな想いがあったのでしょう?
多くの日本企業がせっかく導入したSalesforceを使いこなせていない現実に、強い違和感がありました。素晴らしいプロダクトがあり、様々なローカライズを経て導入しても本来の価値が届いていない。それなら、「その価値をきちんと届ける人間」が必要なんじゃないかと。
過去に私が携わった案件でデジタルやデータを活用した変革事例をみても、例えば 日本の大手耐久消費財メーカーのグローバル案件にはTableauなどのグローバルスタンダードのツールやデータに強いキーパーソンがいて、そのキーパーソンがいたからこそ話が通じ、ディールが決まりました。仮に強い役職はなくても“経営と現場をつなぐ誰か”がいることで、企業は大きく変わる。
日本の老舗企業においても、30〜40代のデジタルが当たり前の世代が経営に参画すれば、デジタル化が加速し、企業価値向上にもつながる。そう考えたとき、「それなら自分がその誰かになればいい」と思うようになりました。
B2B事業立ち上げと“出力”の調整術

「高出力だけでは、人も組織も動かない──その“間合い”を学んだ」
最終的に日系企業であるパイオニア社を選ばれた理由は?
より本質的に組織変革に関わるには、老舗の日系企業の中に入ることが最適だ、と判断しました。比較的経営が順調な老舗企業より、ファンド参画直後というタイミングでファイナンシャルターゲットが明確だと組織が動きやすい。そして、私の担当領域に「ほぼゼロから垂直で立ち上げてくれ」というオーダーがあったからです。CTOの採用からエンジニア50~60名の採用、マーケティング組織の立ち上げまで、ベンチャー的なスピード感で進められる環境に惹かれました。
パイオニア社ではB2B事業の立ち上げを担われたと伺いました。
はい。当時のパイオニアでは、より収益性の高い事業としての柱を作るべく、新たにB2B事業を立ち上げるミッションを担いました。営業、マーケティング、CS、エンジニア採用など、まさに“ゼロから新しい事業をつくるような挑戦”として進めていました。
大きなチャレンジだったと思いますが、どのような壁にぶつかりましたか?
大きな壁として直面したのは、伝統企業ならではの文化と、変革を求める高出力とのバランスでした。スタートアップやIT/デジタル系の企業では成果目標も高く、短期的な成果も求められるため、アジリティが高く、常に5速(最速)で全力疾走できますが、老舗企業でそれを行うと、組織全体での変革には繋がりにくく、むしろ摩擦を生むことになりかねません。特に、外部から採用した合理的な成果志向のメンバーと、長年企業を支えてきた社員との間にカルチャーギャップが生じ、全速力で走ろうとすると組織内に摩擦が起きやすいと痛感しました。
そこで学んだのは、「成果を出すには高出力だけでは不十分」という「出力の調整」や「人間関係や信頼構築の土台」の必要性です。80年以上続く文化や周囲を尊重しながら、どのギアで、どのタイミングで踏み込むか、どこでギアを落とすかを見極めること。これが、組織を変革に導く上での本質的なリーダーシップであり、マネジメントだと気づきました。
その学びが、次のキャリアにも繋がっている?
まさにそうです。小林製薬に転職する決断も、パイオニアでの経験があったからこそ。“信頼関係・人間関係の土台を築きながら、出力の状況を見ながら組織を前に進めていく”という知見を、今度はより強いブランド力と影響力を持つ企業で活かしたいと考えました。ファンド傘下企業とは逆に、変革には時間を要するものの、長期的な視点で経営を行うオーナー企業に身を置きたいと思ったのです。
小林製薬との出会いとCDOとしての挑戦
「“真面目な社長”をきっかけに、私のCDOとしての挑戦が始まった」
小林製薬に入社される前、1年間ほどアドバイザーをされていたそうですね。
はい。きっかけは少し不思議なものでして(笑)。ある夜、共通の知人である足立光さん(現ファミリーマートエグゼクティブ・ディレクター チーフ・マーケティング・オフィサー)とご一緒していたとき、偶然当時社長を務めていた小林氏もその場にいたのです。最初は社長だとは知らされず、自然な会話を楽しんでいた際に「小林です」「小林製薬で働いています」「社長です」と。それが最初の接点でした。
小林製薬に惹かれた理由
「やさしさ」と「違和感」から始まる再構築
多様なキャリアの中で、小林製薬に惹かれた理由は何でしたか?
皆さんとにかくやる気と熱意がすごい。どうにかして会社を良くしたい、DXを成し遂げたいという思いをひしひしと感じました。最初は月に1度は会議に参加して、アドバイスをする立場だったのですが、皆さんの話が盛り上がり、かつ議題も多く、私があまり話せずに終わってしまうこともあるくらいでした(笑)。ただし、それぞれの物差しが違う、前提知識にばらつきがある、やり方がわからない、等 ある種アイドリング状態でしたので、私が貢献できる状況なのではないかと感じました。
そうした“善意同士の衝突”は、入社直後にも感じました。これは、組織に共通言語や視座の多様性が足りないことによるものだと理解しています。だからこそ今、私の役割は「違う物差しを持ち寄って、対話を重ねていくこと」だと捉えています。
実際、私自身が“デジタル”の専門家というより、異なる視点を繋ぎ、問い直す役割としてCDOに就任しています。小林製薬という老舗企業がこれからもう一段変わろうとするとき、その“変化の過渡期”に関わることには大きな意義と責任を感じています。
このスタンスは、今まさにCDOという肩書きを通じて実践している部分でもありますが、実は“CDOという役割そのものが不要になる未来”を目指している部分もあるのです。そのあたりは、後ほど詳しくお話しできればと思います。
“正しいこと”をやり抜く覚悟
「Do The Right Things──それは、誰にも気づかれなくても貫く覚悟」
インテグリティ(誠実さ)とは、石戸さんにとってどのようなものですか?
私にとってのインテグリティとは、「誰も見ていなくても、正しいことを貫く姿勢」です。さらにアカウンタビリティ(説明責任)も強く意識して行動することが、結果的に誠実さにもつながっていくと思います。どちらかだけでもダメなのです。誠実さがあっても、説明がなければ伝わらない。説明が上手くても、行動が伴わなければ信頼は得られない。その両方をバランスよく果たす覚悟が、今、企業のリーダーには求められていると感じています。
経営意思決定と“越境するCDO”

CDOが向き合った文化的壁と変革のリアル
経営の意思決定において、小林製薬ならではの文化的な特徴はありましたか?
これは小林製薬に限らず多くの伝統企業に共通することですが、創業家出身の経営者が大きな意思決定を担うケースが多く、幹部は安定した枠組みの中で判断を重ねる傾向があります。加えて、インバウンド需要の追い風もあり業績が堅調だった時期が続いたため、チャレンジを推奨しつつも「見えない枠組みの中でのチャレンジ」になりやすい。結果として「安定を重んじる」文化が自然と育まれており、これはリスクを避けるだけでなく、企業を長く支えてきた強みのひとつでもあると感じています。
石戸さんご自身は、そのような文化の中でどのように意思決定を支援されたのでしょう?
私がCDOとして意識していたのは、経営を“支える”という姿勢ではなく、経営の“解像度を上げる”役割を担うことでした。たとえば、財務の観点ではP/L中心(売上・営業利益)のスタイルが強いため、稼ぐ力も含めたEBITDAとは何かというところから今後の経営体制の幹部にファイナンス勉強会を実施したり。大きなプロジェクトを進める際の共通OSとして、プロジェクトマネジメントの研修やテンプレート作成など、デジタルに限らず意思決定の基盤となる“思考や業務のフレーム”を少しずつ共通化したり。それらを広げていく試みでした。
意思決定において、石戸さんが最も重視している視点は?
それは“時間軸”です。過去の歴史や文化、癖、習慣を知らないまま「今が正しいから」と変革を急ぐのは非常に危険です。なぜ今この仕組みが存在するのか、なぜその判断がされてきたのか、背景にある意図や必然性を尊重せずに変えると、現場は納得しません。たとえば、2008年の社内報を読み込んだ際、当時の社長も「変革(変身力)」を掲げていました。つまり変革は何度も語られてきましたが、形にするには“歴史への敬意”が不可欠なのです。
“越境”という言葉も使われていましたが、それはCDOの役割と関係しますか?
はい、非常に関係があります。私にとってCDOとは、デジタルの専門家ではなく、“組織の越境者”であるべきだと考えています。経営と現場、経営とIT、営業と製造、暗黙知と形式知、内部と外部、歴史と未来──こうした境界線の間に立ち、相互理解を促進すること。たとえば営業部門は「今すぐ商品が欲しい」と言い、製造側は「品質を守るには供給量に限界がある」と言う。どちらも正しいのです。だからこそ、双方の立場と背景を深く理解し、折り合いをつける。そのために“鳥の目”と“虫の目”を同時に持つ必要があります。
経営判断をする上で表面的なKPIだけでなく、“なぜ現場がそう動いているのか”を聞き取る力、そして調整する力が問われます。単に「AIを導入しよう」とか「デジタル化しよう」という手段先行ではなく、前提として「なぜ今この仕組みなのか」「なぜ過去はそうだったのか」という「なぜ」や「根本的なイシュー」を理解する必要があります。そのうえで未来志向の選択肢を提示していくのがCDOの役割だと思っています。
CDOというポジションが経営において持つ意義はどう変わったと思いますか?
従来のCDO像──すなわち“デジタルを推進する人”という枠を大きく超える必要があると確信しました。むしろ、CDOは「越境して問いを立て、現場の声と経営の理屈を翻訳し、最後に意思決定に責任を持つ人」。経営陣が初めて直面する“自ら決めなければならない”という局面で、どう文化の壁を越え、構造的に意思決定できる仕組みを築くか──そのデザインと実行がCDOの本質だと感じています。
組織変革と“越境学習”による未来展望
「対話と理解に基づく変革(あるいは変化)」を支える“物差し”の再構築と、変化対応力の醸成へ
組織内のコミュニケーションや価値観のズレをどのように捉えていますか?
どの社員も現場では一生懸命に頑張っている。ただ、それぞれが使っている“物差し”が異なるのです。正義や善意を持って頑張っているのに、見ている角度や基準が異なることで、意図せずズレが生じてしまう。たとえば、ある人から見れば「赤」に見えることが、別の人から見れば「黒」に映る。その両方を見て、「赤と黒が混ざっているんだね」「見る方向を変えると色が異なるんだね」と言える存在が必要なのです。皆が真剣になればなるほど、そのズレは広がりやすくなる。だからこそ、共通言語をつくり、視点の違いを理解し合う“ほぐし”が必要になると感じています。
その「物差しの違い」にどうアプローチされているのでしょうか?
私自身がCDOとして取り組んでいるのは、異なる物差しを持つことを否定せず、相対化して見られるようになる支援です。たとえば今、小林製薬の中ではOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)が中心で、体系的な教育システムには改善の余地があります。特に社外との接点や“対外試合”が少なく、社内完結型の学びに留まることが多い現状です。そこで、私が統括する部門では、課長以上の社員にグロービスなどの社外研修に出てもらう取り組みを始めました。半年に2人ずつ外部の世界に“越境”してもらい、自分の価値観や判断軸を相対化してもらうのです。
越境学習によって得られるものは何ですか?
自社の“常識”が実は“非常識”かもしれないと知ること。たとえば、クリティカルシンキングやファシリテーション、プロジェクトマネジメントといった汎用スキルが外の世界では当たり前に使われている。小林製薬は“我流”が多いのですが、それも良い部分と限界がある。だから外で一般的な物差しを学び、自社に持ち帰って自分なりに活かすという循環をつくりたい。今は月ごとにテーマを決め、部門全体でワークショップ形式の学びを実践しています。「今月はクリティカルシンキング」「来月はファシリテーション」といった形で、全員で思考の筋肉を育てていく。いわば“やさしい筋トレ”のような取り組みです。
そのような活動は、今後の組織や日本企業全体にも広がっていくべきだと思われますか?
強くそう思います。日本には100年以上続く企業が多く、その歴史や文化、成功体験が時に変化の足かせになることもあります。だからこそ、過去を否定するのではなく、「敬意を払いながら問い直す」姿勢が大切だと感じています。変化の出発点は、“なぜ変われないのか”を正しく理解することだと思います。
CDOとしての視点で、こうした“人の土台”に注目されている理由を教えてください。
どんなに優れた戦略や仕組みを導入しても、最終的にそれを動かすのは“人”です。そして人の根っこには、変化に対する向き合い方、すなわち「変化対応力」があります。過去を否定する力、尊重しながら変えていく力、批判的に考える力、異なる意見を受け入れるしなやかさ──こうした“ソフトスキル”は特に老舗企業ではあえて言語化されてこなかった部分です。今、それを明確に育成テーマとして打ち出すことがCDOとしての私の責任だと思っています。
“CDOをなくしたいCDO”──石戸亮の覚悟とビジョン
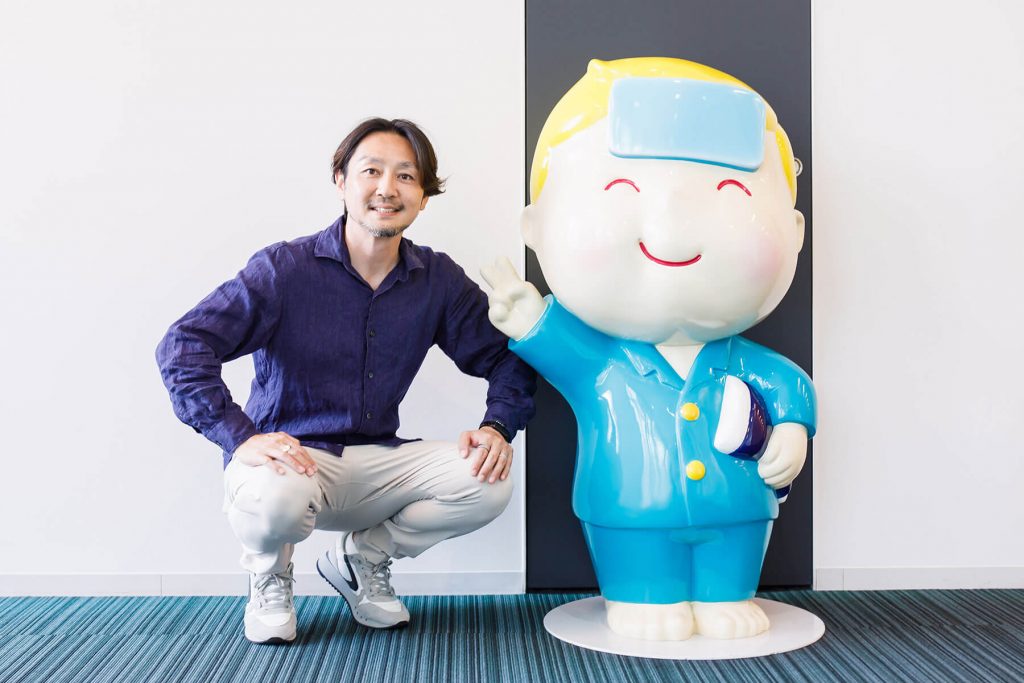
DXは目的ではない、「経営にとっての手段」としてのCDOというあり方
CDOという役割について、石戸さんご自身はどのようなスタンスで臨まれているのでしょうか?
CDOという肩書きはあくまで“手段”だと思っています。DXやCDOという言葉が独り歩きしている場面もありますが、本質はそこではありません。大事なのは「経営にどれだけインパクトを与えられるか」、それだけです。営業方針やマーケティング方針、プロダクト戦略といった経営の中核について、本来CHROもCFOもCDOも立場を超えて議論すべきだと思っています。「私はファイナンスの視点で」「私は人材の視点で」「私はテクノロジーの視点で」と経営の議論に貢献し、そこから“自分のファンクションとしての手段”を選択していく。私にとってのCDOは、まさにその手段の一つでしかありません。
他のCDOと比較して、“自分は違う”と感じられる部分はありますか?
私は「CDOをなくしたいCDO」かもしれません。もちろん最初からその意識があったわけではないのですが、就任後に徐々にそう感じるようになりました。
持論ですが、CDOという役職は5年10年と続けるのではなく、あくまで「変革のための一時的な役割」であって、永続的なポジションであるべきではない。最終的には組織に内包されるべきだと考えています。究極的には“CDOが不要になるほど変革が定着した状態”を目指しています。
入社時にも管理職への自己紹介の時には「DXという言葉を早くなくしたい」と伝えました。DXという概念が不要になるくらい、組織に“変革が当たり前に内包される”ことがCDOとしてのゴールだと考えています。
ご自身のCDOとしての“出口”や、その後のビジョンはどのように考えていますか?
5年後には、たとえば「海外事業部長」や「新規事業の責任者」など、別の立場に移っていても良いと思っています。CDOがずっと存在し続けるようでは本当の意味での変革は起こっていない。その役割が“消える”ことが、最大の成果なのです。
実際、CDOの役割や業務を見ると、会社によって異なりますが、本来はCIO(Chief Information Officer)やCMO(Chief Marketing Officer)、新規事業担当役員、各本部、そして人事・広報・財務・経営企画などの領域に分散・統合されるものです。日本ではまだCDOという名称に過度な期待や誤解がありますが、本来は“足りないところを一時的に補う”有期的な役割。だからこそ、CDOを“終わらせられる”人でありたいと常に思っています。
この哲学は、CDOに限らず、他の職種や役割にも当てはまりそうですね。
まさにそうです。たとえば、HRBP(人事部門の事業部支援機能)も「最終的にはなくなるのが理想」とよく言われます。事業部のメンバー自身が対応できるようになれば、サポートは不要になる。同様に、マーケティングも営業も本当に良いプロダクトであれば最終的には“必要なくなる”。実際、私がパイオニアでマーケティング部門を立ち上げたときも「今は投資しますが、最終的にはマーケティング部はなくなります」と説明していました。だからこそCDOも同じ。究極的には「いなくても回る状態」に持っていくことが、あるべき未来だと考えています。
では、CDOの役割が不要になる未来に向けて、何を最優先にすべきだとお考えですか?
“変われる組織”をつくること、そして“変わり続ける個人”を支援することです。そのためには既存の常識に挑戦し、社内外の視点を柔軟に取り入れていく必要があります。私がCDOとしてやってきたのは、技術や仕組みを導入することだけではなく、“人”や“文化”に手を入れてきたという自負があります。そしてそのすべては、「CDOという役割をいずれ終わらせるため」の準備です。もし次にCDOを名乗る人がいるならば、「自分が最後のCDOになる」くらいの覚悟で臨むべきだと思います。
最後に、未来のCDOを目指す人たちに向けてメッセージをお願いします。
ジレンマを抱えている人、周囲との違和感を持っている人ほど変革の担い手になる素質があると思っています。なぜAとBの間で対立が起きるのか──そうした“間”に入ろうとする人は、時に煙たがられることもあるでしょう。正しいことを言ってもすぐに受け入れてもらえないこともあります。でも大切なのは、自分自身が「どう生きたいか」という軸です。違和感に蓋をせず、一歩踏み出す勇気を持てるかどうか。そして越境力を高めたいなら、まずは身近な場所からでも良い。たとえば、副業的に行きつけの美容室やカフェの経営をちょっと手伝うだけで、財務の知識がマーケティングに応用できたりする。つまり“越境”とは、特別なことではなく自分の枠を少し超えること。その積み重ねが未来のCDOをつくるのだと思います。
ありがとうございました。
Photo by 辻本俊輔
Text&Edit by ISSコンサルティング






 記事一覧に戻る
記事一覧に戻る  業界カテゴリー
業界カテゴリー


 LinkedInを見る
LinkedInを見る